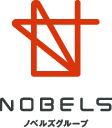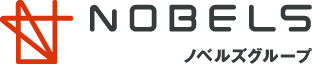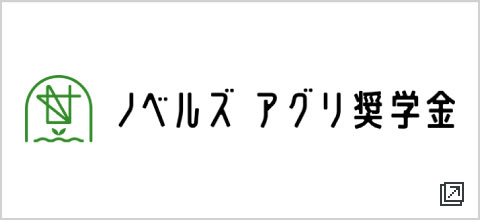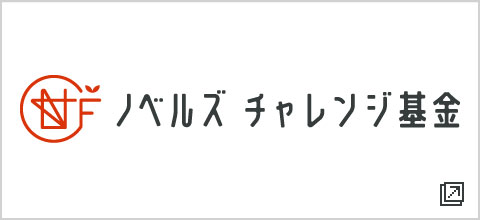地域共生シリーズ④ 飼料向けデントコーン栽培
ノベルズグループの肉牛・酪農・食品の3事業の取り組みを多彩な切り口で紹介する記事広告「地域共生シリーズ」。連載の4回目は、主に酪農牧場で搾乳牛の飼料になるデントコーン栽培をレポートします。
十勝毎日新聞に掲載(2016年12月12日)
地力と収益力高める畑作経営を共創――。
乳牛の飼料に最適なデントコーン。ノベルズグループの委託・自社農場で作付けるデントコーンは約470ha。今後も、新たな委託先を募り、作付面積の拡大を図る計画です。また、ノベルズグループが建設中で、来春稼働予定の清水町のバイオガス発電所から供給される有機液肥の活用など栽培技術の研究にも取り組み、家畜飼料の“地産地消”を推進する考え。ノベルズ農業技術担当杉山勝彦顧問と畑作農家の金田満さんにお聞きしました。

清水町内にある委託栽培農場でのデントコーン収穫作業。大型ハーベスターによる収穫作業は、ノベルズグループが受け持つ
「毎年3%の収量増を目標に」

ノベルズ農業技術顧問 杉山 勝彦(69)
豊頃町出身。JA幕別町で農業土木や栽培指導などに長年携わり、農産部長、常務理事などを歴任し2007年に退任。2016年8月から株式会社ノベルズで技術顧問。
デントコーンに注目した理由は
杉山「輪作体系トータルの収益性向上が期待できます。その根は土中に広く、深く伸びていく。トラクターが踏み固めた固い層も突き破る。根の跡に水や空気が入り込み、微生物の活動が活発化すれば、輪作全体の収益アップするはず」
畑作農家の方々に伝えたいことは
杉山「一気に10%の収量増は難しくとも、3%でならば、どうでしょう。毎年3%ずつ上積めば、所得は飛躍的に増えます。ノベルズグループには、飼料向けデントコーンの大きな需要があり、来春稼働のバイオガス発電所から供給される有機肥料の消化液も活用できます。目下、輪作を考える勉強会を計画中です」
「消化液、後作の研究に励む」

デントコーン栽培農家 金田 満さん(53)
父の代から半世紀以上、47.5haの耕作地で小麦、ビート、豆、ジャガイモなどを輪作してきた新得町内の畑作農家。ノベルズグループと契約し、デントコーン栽培に転換した。
デントコーンを栽培する理由は
金田「2年前、すべての畑をデントコーン栽培に全面積で切り替えたのは、もう周囲の厚意に甘えるわけにいかないとの考えからです。大病を2度も患いながら、やってこれたのは、近隣農家のおかげ。しかし、3度目があってはならないと」
どのような変化がありましたか
金田「春先の播種や除草を終えれば手間がかからず、収穫はノベルズグループが受け持ち、負担はありません。以前と比べて売上減でも増益です。作柄が天候に影響されづらく、体に障る心労から開放されたことが、今の自分には何より大きかったのかもしれません。ただ、収益増へ、消化液や後作の研究は怠りません」
十勝毎日新聞に掲載(2016年12月12日)
〈記事広告「地域共生シリーズ」の掲載一覧はこちらから〉
〈記事広告「地域共生シリーズ」の各回はこちらから〉
※新聞掲載された記事広告「地域共生シリーズ」の各回を本サイトで随時公開します。